「普通においしい」
「ふつうに面白い」
「フツーにかわいい」
などなど、TV、ネット上、実生活で「普通に○○」という言い方を見聞きするようになって、もうずいぶん経っています。
しかし、ずいぶん経っているにもかかわらず、あるいはずいぶん経ったからなのか、この「普通に○○」の意味は人によって解釈が分かれる場合もあって、曖昧なようです。
この表現、元々はどういう意味で使われ始めたんでしょうか?
「普通に○○」の意味を、僕の記憶と解釈の範囲で解説してみます。
(さっさと結論だけ読みたい方はこちら)
現在はどういう意味で使われているのか
「ほどほどに○○」
「普通レベルで」「中程度に」「ほどほどに」といった意味で使われるケースで、「普通に○○」の意味に言及している記事のほとんどがこの解釈のようです。
参考:
教えて!goo
「普通においしい」って褒め言葉?
Yahoo!知恵袋
最近、「普通に美味しい」と言う言葉を聞きますが、
「すごく○○」
元記事のテキストを見つけることが出来なかったので、新聞記事の画像から手入力で抜粋。
「普通においしい?」
何か、彼とは日本語が通じたような、通じないような……会社に戻って、この奇妙な経験を同僚に話すと「普通においしい、というのは、すごくおいしい!という意味ですよ」。
エッ、本当なのか?
普通の「普」は「並」の下に「日」と書く。「並」は横に広がることを表し「通」はあまねく知れ渡っているという意味。だから広辞苑で「普通」は(1)ひろく一般に通ずること(2)どこにでも見受けるようなものであること……とある。この若者は「広く知れ渡ったおいしさ」とでも言いたかったのか? でも「普通においしい」はやっぱりおかしい。
『牧太郎の大きな声では言えないが…』毎日新聞
筆者さんではなく、ここに登場する「同僚」さんによれば、
「普通に○○」=「すごく○○」
だそうな。
さらに、こう続きます。
同僚は「今の若者は、もの心ついてから不況の連続。自分のことを“普通以下”と考えている。だから彼らが言う“普通”とはワンランク上の事なんですよ」
ちょっと考えすぎというか強引じゃなかろうか。
実は「すごく○○」の例はこのひとつしか見当たらなかったんですが、この元記事自体がけっこう知られているようで、複数のブログで取り上げられていたのでここでも挙げてみました。
不定形
「ほどほどに」でも「すごく」でもない中立型(?)の意見もあります。
言う人、聞く人によって意味が違うから気をつけてね、という記事。
それにしても、形容詞はいろいろあるだろうに、なんでどの記事も「おいしい」を例に挙げているんだろう。
以上のように、意味については諸説あるんですが、やはり大勢を占めているのは、
「そこそこ」「可もなく不可もなく」
といったニュアンスでの使われ方のようです。
僕の考える「普通に○○」の元々の意味は上記のどれとも違います。
先に流行った「ある意味○○」
「普通に○○」がどういう意味なのかは、この表現が登場したプロセスを考えると解ります。
この表現が広く用いられるようになるには、ある前振りがありました。
それは「ある意味○○」という表現の流行です。
2014年に終了した長寿番組『笑っていいとも!』に、毎回日替わりでゲストを招いて司会者とトークをする『テレホンショッキング』というコーナーがありました。
もう誰だったか忘れてしまったんですが、ある男性俳優がゲストの回に、
ゲスト「(タモリを)ある意味尊敬してます」
(数秒沈黙)
タモリ「…じゃあ、ある意味じゃ馬鹿にしてるんだろ(笑)」
と、こんなやり取りがあり、客席で地味に笑いが起こるという場面がありました。
「普通に考えると尊敬できるようなことじゃないんだけど、視点を変えれば尊敬できなくもない」
つまり、「よっぽど好意的に解釈しない限り、そりゃダメだよ」という皮肉を含んだジョークですね。
「ある意味○○」の反対語として生まれた「普通に○○」
その放送の影響なのか、その頃からTVで「ある意味○○」という言い回しを耳にすることが多くなったように思います。
流行るにつれて、単に
「先輩、カッコいいっすね」
と言ったら、
「そう? どうせあれだろ? “ある意味カッコいい”ってやつだろ?(笑)」
と軽く自虐ネタで返すという展開も、身の回りで時々見るようになりました。
そしてさらに、
「やだなぁ(笑) 違いますよ。“ある意味”じゃなくて“普通の意味でカッコいい”ですよ。先輩、普通にカッコいいっす」
と続いたりするわけです。
まとめると、
「ある意味○○」があまりに市民権を得て多用されるようになってしまった。
そして、余計な誤解を招かないため、あるいは会話の端々でいやいやヘンな意味じゃないですよ、といちいち返すお約束が面倒になったなどの理由で、初めから「ある意味」じゃなくストレートな意味で言ってると判るように言う必要性が生じた。
そこで使われ始めた接頭語が「普通に○○」である。
と、この表現が登場した頃から僕はそう認識しております。
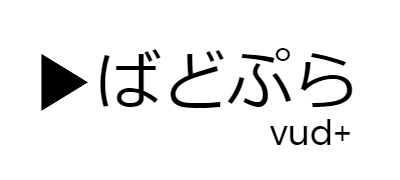
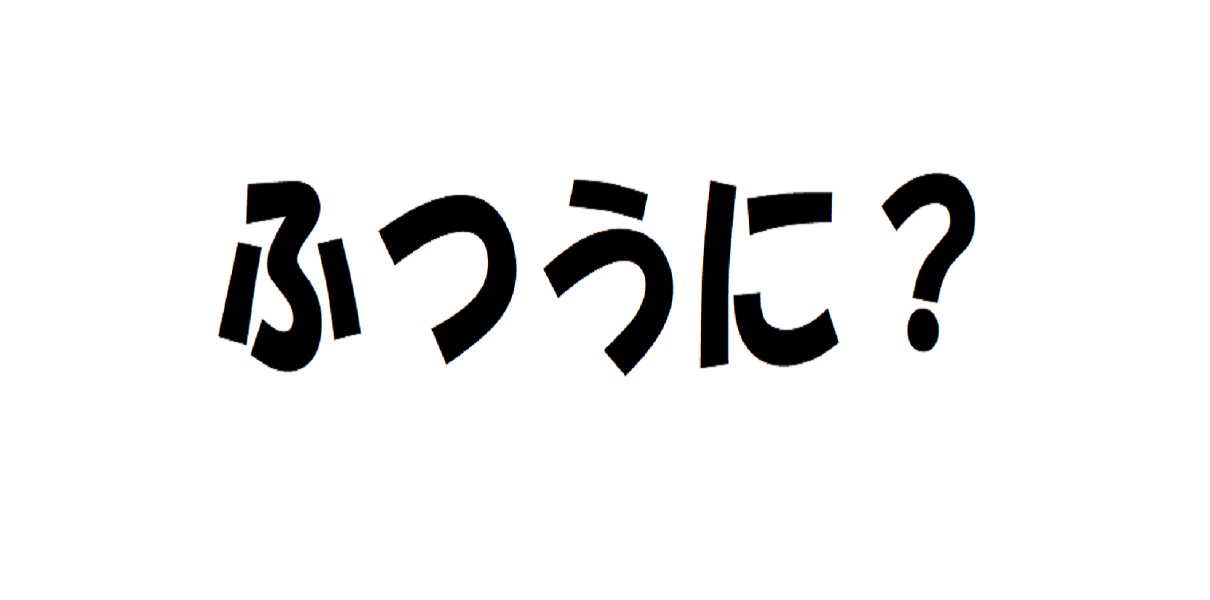


コメント
勉強になりました~。
>さろもんさん
承認中になったってのは、ここのことだったんですねw
「普通に」よりこの記事の「不定形」の使い方のほうがはるかに意味不明です。
「不定形」ってインドヨーロッパ系の言語で、動詞の原形 (主語の人称や数に一致せず、特定の時制になっていない形)のことですね。あるいは化学で「無定形」の同義語。
hknmstさん
コメントありがとうございます。
「不定形」の使い方ついてはこの記事を書く時には特に確認もせず使っていましたが、
広辞苑には次のように記載されています。
ふてい-けい【不定形】 1.形または様式の一定しないもの
私の意図している用法と合致しており、この記事中の使い方で特に問題はないと考えています。